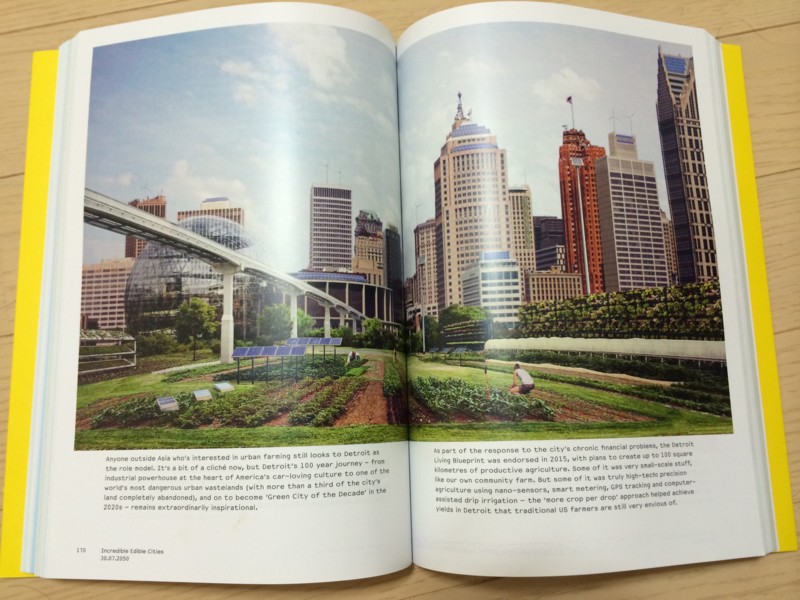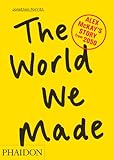James Morrowの新作。この人名前に聞き覚えがあったんだけど翻訳は本としてはないようだ。ただ短編がSFマガジンにはどうも載ったことがあるみたい※@biotit(橋本輝幸)さんに教えてもらいました。ありがとうございます。
190ページ弱なので中編ぐらいの内容なんだと思うが、Kindle版だとページ数表記がないからよくわからない。まあ3日で読めたのでそんなに長くはないのだろう。1950年代の古き良きテレビドラマ黄金時代、中でもとりわけSF、くだらない、やすっぽい話としてのパルプフィクション脚本家たちの一幕を書いた一冊。
先に大雑把な感想だけ書いておくと、かなりくだらなくてそこまで面白いわけではないが、読みどころはいくつかあるといった感じ。
本作において1950年代(1953年)に時代が設定されている意図は、当時のテレビドラマ状況を再現するとか、ノスタルジーに浸る為のものではなく、宗教観が変わりつつある時代における宗教を扱ったテレビドラマ作品の革命をメインに据えて話を創るためのものとして機能しているだけなので、当時の空気感を味わうためには使うことは出来ないだろう。
まあたかだか190ページの物語なのでそう何もかも描写できるわけではない。宗教風刺について、「こんな内容を描いて、本当に許されるのか!?」みたいなサスペンスのノリで展開していくが、宗教文化の前提を持たない僕のような読み手からするとどうにもよくわかんなかったな。つまり、神に対してのフィクション上のお遊びとして、どの程度の冒涜が許されて、どの程度は冒涜とみなされないのかその境目がどうにもぴんとこない。実際本作で冒涜的とされているシナリオも「そこまでいうほどのものか?」と思ってしまったし。もちろん「これは相当な冒涜なんだろうな」とノリを合わせて読むことはできるので本質的な問題ではないだけど。
物語の主役Kurt Jastrowはフルタイムのテレビドラマ脚本家で、自分が執筆しているSFドラマのエピローグでメタ的に作品内で行われている科学的説明を子供に向かってするという役者の役目も行い、時たま小説も書くというなかなかのやり手である。しかし突然青いロブスターっぽいQualimosansという地球外惑星からやってきた論理実証主義者がやってきてKurt Jastrowのファンだと宣言し、トロフィーを勝手に与えてくる。それだけなら気の狂った良い宇宙人もいるようだなといって終わるはずだが、たまたま見たドラマのリハーサルが「パンは肉に変わるし病人はたちどころに治るしこんな番組を見ている奴らは非理性的なクソどもだぜ。非理性的なヤツラは全員大虐殺だぜ」と無茶苦茶なことを言ってくるのであった。
なんだそりゃと言いたくなるし読んでいて「なんだそりゃ読むのやめようかな」ぐらいは思ったが、作中人物的にはこんなことを言われたらなんとかしないわけにはいかないのでKurt Jastrowとその想い人Connieは青い甲殻類に完膚なきまでに否定された宗教シナリオを宗教に風刺的な内容にリライトする羽目になったのであった。これは今でも存在するのかどうかわからないが、特定の枠にreligious programのように、宗教宣伝を目的としたようなドラマを放映することがあったらしく、今回青い甲殻類に批判されたのはこのドラマだったらしい。
面白いかと言われればそんなに面白くはないが、読みどころはいくつかある……と最初に要約して書いたが、「そんなに面白くない」の部分は、今どきこんなコミカルに宇宙人がきました的なノリを小説でやられてもどう受け止めていいのかわからないというのがある。うまくこうした宇宙人が物語の中で機能しているのならばいいんだけどなんか本当に、ただ「シナリオの書き換えを促すだけの存在」として描かれているようで、「それこんな無茶して宇宙人出す必要あるか?」という。こんな文章を大まじめに書かれてどう反応していいのかよくわからなかったよ
Before we sought you out in conference room C, I used this transceiver to contact Yaxquid, the navigator of our orbiting spaceship. From beneath her carapace Wulawand produced an object suggesting a green ocarina. "Acting on my orders, he placed our X-13 death-ray projector on standby alert Come Sunday morning, shortly after the Bread Alone cult has gathered around their television sets─"
death-rayとは笑いをとろうとしているにしてもまあちょっとひどすぎる気がする。こういうものなんだろうか、こういうもののような気もするなあ……。受け手の僕側の問題かもしれない。パルプ・フィクション脚本を書く脚本家たちを書いた本作もまたパルプ・フィクションであることは自明であり、パルプ・フィクション論にもなっているのが本作の特徴の一つではある。だからこそこうした自己言及的な、明らかに自覚的な古臭い安っぽさ、安易さはメタ的にギャグとして楽しめるのだろう。イマイチノリきれなかったが。
宇宙人以外の部分でいえば、企てている所の意図がわからないわけではないが……ようは宗教的な考えが優勢な時代において科学的な考証を必要とする流れがうまれて、そのどっちもをどたばたしながら行き来するという視点にある種のパルプフィクションとしての喜劇的面白さと宗教観に揺さぶりをかけるテーマ的な面白さが両立されているのだと思うが、まあさっき書いたようにここはどうもぴんとこなかった。
逆に読みどころはどこかといえば、1950年代の脚本家や役者同士のやりとり、空気感かな。毎週火曜日にKurt Jastrowと脚本家仲間が集まって自分たちが毎週請け負っているシナリオの問題点などを指摘しあう検討会を行うんだけど、この時の「君の脚本ぜんぜん矛盾してるんだけど??」「いやいやそれは矛盾してるんじゃなくてね……」「私こんなのやってたらテレビのチャンネル変えるわ」「俺は変えない!」みたいなクリエイター同士のブラッシュアップの過程がまず面白い。そしてKurt自身が、著者のパルプフィクション観、SF観の表現にもなっている。
“‘Tangible nothingness’? Really, Kurt, that’s a contradiction in terms.”
“No,it’s science fiction,” countered Howard, muting a strip of bacon. “it doesn’t have to make sense.”Of my three fellow Underwood Milkers, only Howard was unseeingly sympathetic to Brock barton, though he seemed incapable of exhibition this loyalty withoute making condescending remarks about science fiction per se. “if I were a kid encountering Kurt’s spectral sphere, I’d think it was swell.”
“And if I were a kid encountering Kurt’s spectral sphere, I’d switch channels to Crusader Rabbit,” said Connie, pouring syrup on her French toast.
あとはドタバタとリライトを重ね役者とプロデューサーを説得しなんとかかんとかリハーサルを終えて「俺達は面白い、革命的なものをとったぞ!!」と興奮している時の虚脱感伴う描写がいちいちしっくりくる。こういう要所要所の描写が実にさり気なくいかしていて読むのが愉しい。
The rehearsal ended shortly after 11:00 P.M. I bid Marshall good night, gave him ten bucks for his troubles and, taking hold of my valise, climbed the stairs to Connies sanctum I entered quietly, knowing sh might be in the midst of a creative meditation, but instead I found her talking on the phone.
With a wary eye I surveyed the console, a science-fictional installation comprising the switching device, the audio mixing board, and bank of small monitors labeled camera 1, camera 2, camera 3, preview, air, and film chain. Everything seemed fully functional. Connie cradled the handset. Having discarded Lennny’s motorcycle jacket, which now hung over the back of the technical director’s chair, she presented herself to me in the same maroon silk blouse she’d been wearing since we left the studio on Friday afternoon.
他に特に印象的だった場面といえば、冒頭でKurtが自己紹介的な独白をしているところだったな「なぜ幸福をつかむ場所としてニューヨーククを選んだの?」という質問にたいして僕はいつも「木の為にきたのさ」と答えている。この納得のいかない答え、木ならペニーシルバニアでもどこにだってあるじゃないか──といった疑問にたいして即座に答えを付け加える。
『That is, I came for the greatest of all the good things trees give us, better than fruit or shade, better than birds. I speak of pulp』つまり木は木でもパルプ・フィクションの為だよ~んというなんかこう改めて読んでみると人をナメくさったような受け答えだが、キザでかっこ良くしかし言ってるのはパルプ・フィクションへの愛というどうしようもない感じが良い。
全体的に宇宙人が関わってくる部分については納得いきかねるが、それ以外のシナリオをブラッシュアップしていく過程、シナリオをリライトして俳優人やプロデューサー人を説き伏せて、なんとか放映までに改変を終えようとする至極まっとうなパートについては満足いく内容だった。本書の題名になっている『The Madonna and the Starship』はこの作中作で改変が行われたシナリオの題名で、地球生まれの宗教が銀河を汚染する前に宇宙人が阻止しにくるような話になっている。