やはり、ファンタジーとえば王であろう。そう思いませんか? 架空の国をつくりあげて架空の人々、部族の習慣を練り上げて、新しい世界を創造するのがファンタジーだが、架空の国には王がいるものだ。そして架空の国で、好きなように物語を展開させていけるのだから、そこにはやはり王が絡んでくるものだ。そしたら話がでかくなる! いやいやそらハリーポッターにゃ王なんておらんし、そもそも国をつくったりしない、王の出てこないファンタジーだっていくらでもあるけど、やっぱり僕は指輪物語や氷と炎の歌シリーズやなんやかやを溺愛しながら読んでいるわけで王の出てくるファンタジーに特別な気持ちを抱いている!
王が王になっていく展開も好きだし、脇役としての王がかっこよく決めるのも好きだし、愚鈍な王が民衆に殺されたり腹心の部下に殺されて国に革命的な変化が起こっていくのも好きだ……愚鈍な王も聡明な王も傀儡としての王も武闘派の王も王は王であるというだけで物語に嫌でも影響を与え、そしてその影響力の大きさゆえに素晴らしい……。そう思いませんか? で、日本が誇るファンタジー作家上橋菜穂子さんの新刊がこの『鹿の王』だ。しかも上下巻できっちり完結してくる、王ですよ王。
これはもう超王道のファンタジーに違いあるまいと、上橋菜穂子的主人公が、鹿の王になるまでの壮大な人生を描いた物語に違いないと期待に満ちて読み始めた。事前予想を完全に外しながらも期待を裏切らないファンタジー作品に仕立てあげられている。そうだった。上橋菜穂子はそういう作家ではなかった。国対国といったその中心を描くのではなく、もっとなんというか、小さな部分、周縁の部分、巨大な国家の中で賢明にいきていく人間を描いていくことで、同時に大きなものも描き切っていく、そういう作家だった。僕が間違っていたのだ。
あらすじを簡単に説明しておくと、かつて辺境の部族において物凄く強かったとされる戦士団『独角』の頭領だったヴァンという男が、敵方に捕まった後奴隷として働いている所から物語は始まる。しかし労働場に突然犬たちが襲いかかってきて、おそらくはその犬をきっかけにして謎の病が発生する。その現場では唯一ヴァンと幼女が一人生き残りかけて脱出を図る。一方国の医師として勤務するホッサルは、突如発生した謎の奇病に対して病の解明と、対処を迫られ試行錯誤を繰り返していく──。病の発生原因は、病の蔓延を食い止めることはできるのか。
というわけで基本的にはヴァンとホッサルのダブル主人公体制によって話が進んでいく。ヴァンは犬に襲われながらも病気に打ち勝った貴重な被験体であり、この時のことにより不可思議な能力を持つようになっている。対するホッサルが駆使するのは観察、実験、検証、また実験の科学的プロセスだ。ファンタジーと科学的プロセスとはいっけん馴染まない要素のように直感的に思うが、上橋菜穂子作品においてはそれは世界観をより深めていくプロセスのひとつであり、架空世界において現実感を増していく説得力の一つとして機能していく。
割り切らせない物語
病、というのが今回大きな問題となって持ち上がってくる。ヴァンが侵される病であり、ホッサルが闘うべき敵である。通常ファンタジーといえば国と国との闘争が主な目的になるところだが、本作の場合はそれが形を持たない病となっているところに、一つの面白さがあるといえるだろう。たとえば病というのは、なかなか根絶するものが難しい。国家間の対立なんてものは、まあいってみればわかりやすいものだ。最悪叩き潰せばいいんだから(これは非常に単純化した例だけども)。
病はあそこに敵がいるぞー! たたけー!! といって殲滅させられるものではない。発生原因を特定して、薬効や対処法を確立して、感染する病であれば患者は隔離して……そこまででも膨大な手間がかかるのに今度は病が変化してこれまで通りの手段で防御できなくなることへの対抗策や薬が誰にでもきくのか、拒否反応が出る人間はいないのか、といった細かい検証も必要とされていく。そしてそこまでやっても完全に消滅させられる病ばかりでもない。
ようは病を主軸にして物語を書く、それも「ちゃんと病を書く」ということは、割り切れない領域へ踏み込んでいくことだ。簡単に根絶できるものではなく、わかりやすく大団円を迎えるのは難しい。人類がいまだに病を根絶できていないのだから、ある意味それは終わりのない戦いともいえる。この割り切れなさ、単純な答えを物語として与えられない終わらなさは、病以外の部分にも適用されていく。国家と国家の争い、人間と人間の関係、「仲間を守るために自分の命を危険にさらす」ことの是か非か、といった小さなテーマも、「仲間のために命を危険に晒せるヤツは勇気のあるかっこいい人間だ」と単純には割り切らせてくれない。
でもその割り切れない中で先に続いていくものがあるのだと示される物語だったと思う。僕は途中まで本作をどう評価していいのか迷っていたところがあったのだけど、その割り切れなさこそが本作の焦点であったのだと考えるようになってから、ようやく自分の中での評価を定めることができた。
病それ自体は眼に見えないものの、自己増殖する生命としてふるまう。だからこそ人間の性質と似てくるものもあるし、人間の集まった国家との類似も多くみられる。本作は病を物語の主軸とすることで、病を語るのと同時に人間のありかたそのものを語り、そして人間そのもののありかたを語るのと同時に国家をもそのアナロジーに巻き込んでいく。
人の身体の内側には、多くの目に見えぬ生き物が住み着いていて、己の住み処である人の身体を生かしている、という事実は、<諸国を活かし、自らも生きよ>という標語を心の支えとしてきたオタワル人にとっては、実に愉快な発見であった。
国を持たないということは、己の身体を持たぬようなもの。それでも、オタワル人は微小な生き物のように、様々な国々に入り込み、偏在して、その国々を豊かに活かしてきたのだから……。
このミクロからマクロまでもを一度に書き切ってしまうことができるのが、上橋菜穂子さんの作家としての能力、その芳醇さを感じさせる。
世界観について
ミクロからマクロまでを書ききるといえば、世界観の構築からしてそうした思想がみえる。上橋菜穂子さんのファンタジー作品って、全く個別の、一から立ち上げられた世界なんだよね。ファンタジー作家の中にも明らかにこの国家のモデルはドイツだろ、とかロシアだろ、とかそういうのがわかるように書く人もいるが、上橋菜穂子さんは世界に我々の世界からの起源を感じさせない、一から立ち上げた架空世界を構築していく。これは別にどちらがいいという話ではないが、ファンタジー世界が我々の世界とは全く別の、起源を感じさせないオリジナルであることは、読者にとっては没入感を高める効果はあると思う。我々はそこに現実社会の片鱗をみない。だからこそそこに自分自身を捨てて入り込んでいくことができる。
一から世界を立ち上げる。言葉にしてみれば簡単なようにもみえるが、そうそうできることではない。元ネタがないということは、そこの国や歴史、部族といったものにそれだけの説得力がないとウソっぽくなってしまうのだから。匂いから色、部族の昔からのしきたり、歴史からくる考え方の成立過程、架空動物の細かな仕草、特殊な習慣、各国家群の微妙な思いみたいなのが丁寧に積み上げられていった先にしか成立しないものだ。たとえば本作では飛鹿という架空生物の細やかな生態から、部族のしきたり、国家の成立過程まで幅広くこみいって世界が描写されていく。この描写がまた凄い。
飛鹿は、他の鹿とは随分習性が違う。
群れはあるのだが、母仔以外は、どの範囲が同じ群れなのかわからぬことがあるほど、ばらばらに広がっていることもある。
そんな風に独立不羈の気性が強い鹿だが、寂しがり屋のところもあって、不思議なほどに忠誠心も強い。仔のうちに絆をつくると、生涯忘れることなく、口笛ひとつで寄ってきてくれる。
季節ごとに移動はするが、彼らは必ず通る道というのをつくる習性があるので、森の要所要所にモホキを生やしておけば、群れを巧みに管理することができた。
物語の主人公の一人であるヴァンは飛鹿と共に生きてきた部族の、その中でも飛鹿を駆るのが抜群にウマいという人物なので、とにかくこの飛鹿とのエピソードは尽きない。過去を振り返ればそこには飛鹿がいて、彼の判断・行動基準にもからまってくる。そうしたエピソード一つ一つが飛鹿の習性や習慣、種族の特徴への説明になっており、この世界には確かに飛鹿というものがいるんだ、と素朴な実感が立ち上がってくる。
むかし、父が言っていた。どう言い繕おうと、おれたちは飛鹿を自分たちの都合で使っているのだと。それを決して忘れるな。勇壮な歌で己の心を鼓舞しながら、その裏で、飛鹿よ、すまんなぁ、と許しを請うている情けない者──それが飛鹿乗りなのだ、と。
人間と人間以外の動物の特殊な関係って、上橋菜穂子作品では毎度顕著だけど、ファンタジー世界ならではの結びつきからくる関係性だと思う。僕も本を読んだぐらいでしかしらないけど過去の戦争時の騎馬兵の馬と兵士の関係性に近いかな、こういう精神性って。よく言葉も通じない獣に命を預けられるなと思うけど、でもそこには言葉を超えた意志の疎通が完全にはかられていて、家族以上の関係性として成立している。
上橋菜穂子的カッコイイ男女
そしてその関係性に安住しているのではなく、引用部のように「すまんなぁ、と許しを請うている情けない者」という信頼と利用していることにたいする相反した感情も同時に描写しているのが非常にしっくりくる。この申し訳無さを常に抱えている、少し情けない部分って、上橋菜穂子さんが描写する「カッコイイ男」に共通している要素のような気もするなあ。上橋菜穂子的カッコイイ男は、各作品を読んだ人にはすぐに分かってもらえると思うのだが、みなとても有能なのに強烈な孤独を抱えていて、しかしそれでいて惨めな感じはない、孤高の狼のような人達なのだ。
本作の主人公ヴァンはまさにその正統派で、物静かで口数は多くないが、同時に若者や奴隷として働いていた現場で拾ってきた幼女に対しては優しさと思いやりをみせ、ほがらかな明るさを感じさせるナイスガイだ。本書のあとがきで『駆けて行く男の背中を、一生懸命追って行く、かわいい、幼い娘の姿が見えた時、あ、書ける、と思いました。』といっているが、まさにそのイメージ通りの、自分の信念にしたがって駆けて行く男と、その周りにいる、彼を放っておけない人達という構図が、ハードな展開を迎え続ける本作を明るい雰囲気で包み込んでいく。
また周りの人達がいいんだよね。上橋菜穂子さんの作品に出てくる女性もみな自分の状況にへこたれず力強く立ち向かっていく有能な人が中心となることが多い。その過程で自然に夫婦となったり、男女の関係になっていくこともあるが、それらは決して従属的な関係ではなく、お互いの能力と人格を認め合った上での対等の関係として描かれていく。才はある意味では残酷だとこの物語の中では語られる。ときに才が、それを持つものを死地に押し出すから。他者が追いつけない速度で駆けて行くヴァンとホッサルという男に、しかしその周りには彼らに親しみを持ち、彼らを支援し、追いつきたいと願うものがいる。才あるものは駆け、周りの人間はそのあとを懸命においかけるというその構図は、才の持つ残酷さを中和させるものとして、美しくうつった。
これまでの上橋菜穂子作品を踏まえつつ、これまで書いたことのないものを書き、これまで書いてきたものの先を書くような、総じて完成度の高い一作。今ならカドカワセールによって、電子書籍なら紙の本の半額の値段1600円で買うことができる。※追記 Amazonがまだ変身を隠していたようで今みたらさらに割引され1382円になっていた。すげえ安いなおい。ちなみに僕はしっかり3200円出して上下巻買いました。ぐぬぬ。

- 作者: 上橋菜穂子
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/角川書店
- 発売日: 2014/09/24
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (5件) を見る
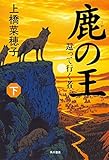
- 作者: 上橋菜穂子
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/角川書店
- 発売日: 2014/09/24
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (4件) を見る

- 作者: 上橋菜穂子
- 出版社/メーカー: KADOKAWA / 角川書店
- 発売日: 2014/09/25
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る