チャールズ・ストロスによる長編スペースオペラ。相変わらず時代はずっと先で、人間はsoulをチップに入れバックアップをとることができ、当然ながらsoulだけを情報として別の場所に送ることもでき、銀河系全体に人類が広がっているおかげで経済の仕組み自体も大きく変わっている。そりゃまあそうだろうなあ。まあようは我々が知っている現代とも、ちょっと先の未来とも全然違う、未来世界だ
語り手のKrinaは姉であるAnaを最初、自身の就職活動の為探している。Anaを就活で頼りにしていたのに、突如連絡がとれなくなったので、情報を集めに彼女の行方が知れなくなった場所まで、まずは移動することにしたのだ。カネがないがなんとか潜り込んだ宇宙船で今度はなぜか自身を目的とした海賊船に遭遇してしまい、Krinaは大変な事態へ巻き込まれていく……というのがおおまかなあらすじ。
もちろんチャールズ・ストロスの長編なので中身はハードな未来描写が渦巻いている。KrinaとAnaは同一の情報を元にしたメタヒューマンであるし、人間(といっていいのかどうかよくわからないが)はその身体を水性生物にでもなんにでも換装することができる。元々からして宇宙空間や海底でも活動できるように身体を徹底的にリ・クリエイションされていて、そもそもバックアップがいるので死に対しての観念が現代人とはまったく異なる。
まったくことなる状況、まったくことなる前提へと想像力を飛躍させることで、さまざまな情念を発動させるのがSFの一つの醍醐味ではあるが、ここまで現代人と隔たっているとなかなか入り込むのも難しかったりする。その突き放しっぷりがまた、魅力ではあるのだけれども。ただノーフォローかといえば、時折みせる普通の人間的感情だったり、ずっと未来の話のはずなのにやけに現代っぽい喩え話などはちゃんとなされている。*1
ただ舞台設定がいろいろと作りこまれている反面(もっとも宇宙船が飛んでいる仕組みとかほとんど説明されない部分との楽さが大きいのだが)、中で展開されるプロット自体は宝探し、人探し、突如襲ってくる宇宙海賊、となんだか昔ながらのスペース・オペラだね〜〜と言いたくなるようなシンプルさ、わかりやすさ。これはまあ、ストロスぐらいごてごてと世界設定への描写に重きをおくと、プロット自体はシンプルな方が良いのかもしれない。これでプロットまで複雑だとついていけない。
Slow money
主人公であるKrinaからして、経済学史の研究者であることからもわかるように、本書で中心をなす要素は経済である。光速で一年以上隔たった惑星間にいる人間同士による経済活動はどのように可能か、というストロスが考えだしたアイディアが中心になっていく。そういえば僕が読んできたあまり多くはないスペースオペラでは、ワープ航法があったり、極度に離れた場所までは利ざやを稼ぐ宇宙の運び屋がいたりして、深く考えている作品をみたことがない。
それではいったい全体どうやってストロスはそれを解決する方法を考えたのか? まずこの世界ではお金を3つの分類にわけて考えられている。fast moneyはその名前の通り、手早く決済が可能な「現金」のこと。medium moneyが土地や株などのように、すぐには変えられない「資産」のこと。ここまではわかりやすい、現代にもあるものだ。しかしもし惑星間で、10年も経って家や土地を換金しようとしたら価値が極端に変動してしまってまっとうな取引なんかできっこないだろう。
そもそも10年も経ったら実際のブツが消失していてもおかしくはない。取引が完了しましたー、げえ、家がない! あ、取引はなかったことにしてくれ……なんてことになったら誰も取引なんてしないだろう。そこで最後に、これを解決するために本書オリジナルの概念としてslow moneyというものがでてくる。これはようは金のやりとりに強制的に数年を要する決済方法で、確実にその支払処理が実行されるように第三者の星系による銀行機関によって保証されるような仕組みになっている。
たとえば別星系において僕があなたのsoul copyを労働者として、10年単位で雇ったとする。その場合支払いはSlow moneyで行われ、これは第三者の銀行機関に保証される。金のやりとりは銀行を介在して行われる。最初に金を受け取る時に、一度受け取ったものにサインをして保証をしてくれた銀行機関に送り返し、その認証が通って初めてアクティベーションされるのだ。
これらはすべて遠く離れた惑星間を通してやりとり、往復されるために、必然的に換金されるまでに数年を要する。この取引の遅さがあるせいで、slow moneyという呼称になっている。七面倒臭いシステムだが取引が終わってみたらもうその物はなかった! なんて自体にはならないのだからこれはこれで必要なことなのだろう。
壊れやすい身体、ひとつの惑星に縛られた人類
ストロスの作品はぶっちゃけハードSFにありがちな、テクノロジーの描写に傾注してしまったあまりに、キャラクタの魅力が全然なかったり、プロット自体があんまり惹かれるものではないという非常に残念な欠陥を抱えていると思う。それにギャグでやっているのかまじめにやっているのかよくわからない頓珍漢な描写があったりして(僕の読解力の問題かもしれないが)とても全部が好きにはなれない。
全部が好きにはなれないのだが、それはそれとして、こうやって果敢に何百何千年も先の未来を描いてやるぜ、人間を全く別の生命体につくりかえて、その全く別の生命体とかした人間が織りなす社会を書いてやるぜ、壊れやすい人間を克服し、一つだけの惑星に縛られていた人類を超越し、遠くまで広がっていった世界を書いてやるんだ、っていう意気込みとアイディアの奔流は毎度楽しくて、今どきこんな楽観的な、宇宙に広がっていく人類像を書く人間もなかなかいないだろう。
イーガンほど人間離れさせない、ストロスの間合いがあるんだよね。本作もその独特の間合いが十全に発揮された、良い長編だった。

- 作者: Charles Stross
- 出版社/メーカー: Ace Hardcover
- 発売日: 2013/07/02
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る
*1:あるいはそれは読者に最低限でも合わせるために日和った描写といういいかたもできてしまうものかもしれないが。









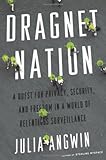



![S-Fマガジン 2014年 04月号 [雑誌] S-Fマガジン 2014年 04月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51y8cK8JyLL._SL160_.jpg)





