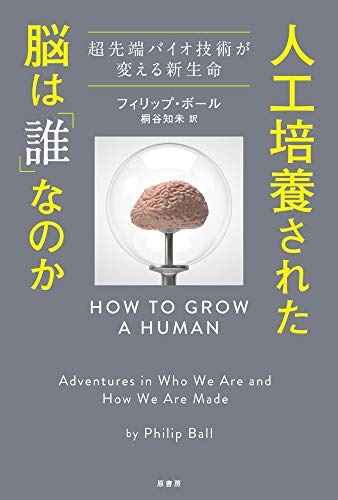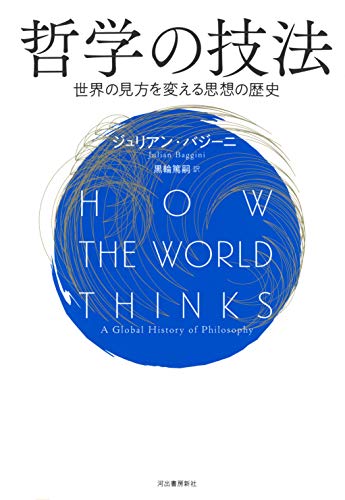まえがき
本の雑誌 2020年6月号掲載の新刊ノンフィクションガイドをここに転載します。連載六回目。なかなか書き慣れてきている感じがしますね。トップのフィリップ・ボール『人工培養された脳は「誰」なのか 超先端バイオ技術が変える新生命』はブログでも紹介していないのだけれども、まとめ方が難しくて断念した本。
ブログで書くなら最低でも2000字ぐらい、2500〜3000字ぐらいは欲しいかなという個人的な感覚があり、頭の中でその本で3000字書くとしたらどういう構成になるかなと考えるのだけど、うまくまとめる切り口がないと流れてしまう。本の雑誌連載だと一冊あたり多くても600文字程度なので、要点がおもしろい作品の場合サクッとまとめて紹介できるのでけっこうブログに紹介していない本も取り上げてます。
あと今回おもしろかったのは落ちぶれたディズニーを復興させたロバート・アイガー元CEOの『ディズニーCEOが実践する10の原則』。この本、アイガーの豪腕が語られててめちゃくちゃおもしろかったんだけど、凄まじい権力欲求とそれにまるで相反するような他者への敬意とか尊敬が語られていて、こういっちゃあなんだけど敬意とか尊敬の方ってフェイクで、中身は他者をなんとも思っていないサイコパスじゃないとここまで成功できないんじゃないかな……という恐怖も感じる一冊である。
新刊めったくたガイド
今回まず紹介したいのは、フィリップ・ボール『人工培養された脳は「誰」なのか 超先端バイオ技術が変える新生命』(桐谷知未訳/原書房)だ。原題は「How To Grow A Human」で、受精した後、どのような仕組みでヒトの機構が形作られていくのか。その仕組みを外に持ち出して、ゼロから人間を作ることは可能なのだろうか? と生命の創造について問いかけた一冊である。
人工培養脳や、ヒトの細胞を持ったブタの胎児を作り上げる実験、遺伝子編集を加えたデザイナーベイビーの可能性など、細胞生物学の進歩によって可能になった事象と、そこから巻き起こる哲学・倫理的問題をいくつも取り上げていく。仮にヒトの器官をブタの中で育てることができれば、臓器不全に直面する何千もの人々を救う手立てになりえる。一方で、ブタを臓器工場にするのは許されることなのか、ヒトとブタのキメラを生み出すことへの直観的な嫌悪感など、倫理的課題は多い。
中国ではすでに、エイズに耐性を作る目的でゲノム編集を加えた双子が産まれたことが報告されている。まだ広く存在しないからといって、議論を先延ばしにしていいわけではないのだ。本書は、細胞生物学の基礎的な知識を概観することもできる他、そうした未来の議題について、考える端緒となってくれる。
続けて紹介したいのは、「世界をどう見るか」や「どのようにして物事を考えればよいのか」についてのヒントを与えてくれるジュリアン・バジーニ『哲学の技法 世界の見方を変える思想の歴史』(黒輪篤嗣訳/河出書房新社)だ。「洞察」「時間」「言葉にできないこと」などテーマごとにそれぞれの哲学がどのような答えを出しているのかを語り、その哲学が受け入れられている国の文化や物の見方にどのような影響を与えているのかといった視点が挟まれていく。我々は自分の倫理観や道徳観、人生の意味についての考え方は「自分が考え出したもの」のように感じているが、実際には自分が所属する文化と深く関係しあっていて、その枠の中で考えているのだ、という普段意識せざる限界を実感させてくれる一冊である。
次は人間以外の知能がどうやって思考するかについての一冊、ショーン・ジェリッシュ『スマートマシンはこうして思考する』(依田光江訳/みすず書房)。自動運転車や、囲碁で人類最強になったAlpha Goなど、これらAIの動作原理は大きく異なっている。たとえば自動運転でいえば、どうやって走っていいルート=道を検知するのか? 障害物があったとして、それをどう避ければ良いのか?など対処すべき問題は数多い。類似した色の画素をグループ化する機械学習の一手法「クラスタリング」を使って道路の縁を検出し、センサーが検知した物体をディープラーニングでカテゴリ別に分類し──と、「そこで何が行われているのか」がコンピュータ科学の知識がない人間にもわかるように書かれているので、しっかり理解したい人にオススメだ!
二〇〇五年、映画事業が落ち目だったディズニーのCEOに就任し、そこから一五年で時価総額を五倍、ピクサー、マーベル、ルーカス・フィルム、21世紀フォックスまで買収してみせた驚異の男ロバート・アイガーによるビジネス回顧録が『ディズニーCEOが実践する10の原則』(関美和訳/早川書房)だ。そうした圧倒的な成功体験を今まさに築き上げているさなかにも関わらず引退を決断するなど「引き際の見事さ」も凄い。全米ネットワークテレビ局のABCに下っ端として入社し、評価されトップにまで上り詰めていくのだが、『ほんの少し敬意を払うだけで、信じられないようないいことが起きる。』といった仕事哲学が語られるだけでなく、大型買収を仕掛ける際のとんでもない苦難など、ビジネス戦記として読んでも抜群におもしろい。
二〇二〇年の一月に、全世界共通の地球の地質年代の一つとして、「チバニアン」が採用されることになった。『地磁気逆転と「チバニアン」 地球の磁場は、なぜ逆転するのか』(ブルーバックス)は、そもそもチバニアンとは何なのか、その歴史的意義は何なのかを、古地磁気学の研究者で今回のチバニアン認定を推進した研究グループの中心人物である菅沼悠介が解説した一冊である。実は北と南を示すN極とS極は、地球の長い歴史では幾度も「反転」しているのだが、それが判明したきっかけとして、千葉の房総半島の地層が関係していて──と、磁気反転と千葉の関連が紹介されていく。まだわかっていないことも多く、隕石衝突が地磁気逆転のトリガーになっている可能性、地磁気逆転と生物の絶滅・進化の関係性など、千葉の一地域から壮大な数億年単位の話に繋がっていく、スケール感を感じられる一冊だ。
最後に紹介するのは、スマホとSNSの登場によって激変した「写真」の現在を描き出す現代写真論である大山顕『新写真論 スマホと顔』(ゲンロン叢書)だ。スマホの登場によって誰もがカメラを持ち歩き、そこにSNSが合わさることで、撮った写真を即座に人にみせることができるようになった。かつては「記録」であり、「なんとなく」撮られていた写真が、今では積極的に人にみせ、自己アピールをするための一手段となった。高度な画像編集技術やノウハウがすぐに広まる現在、写真の質は横並びになり、代わりに「何処で」「誰と」撮ったのかが重要になってゆく。そうした歴史と変化を丹念に追うことで、読み終える頃にはスマホ&SNSの以前と以後で、「写真」の捉え方がまったく違うものになったと感じられることだろう。
おわりに
今月号の本の雑誌もよろしくね。『ゼロからつくる科学文明』、『宇宙考古学の冒険 古代遺跡は人工衛星で探し出せ』、『コンピューターは人のように話せるか?』などいろいろ紹介しています。