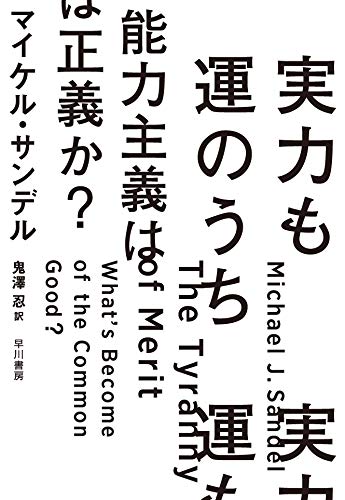はじめに
他者の身体や私的財産を侵害しない限り、各人が望むすべての行動は自由であると主張する、リバタリアンと呼ばれる人たちがいる。すべてを自由にすべきと考える原理的な人から、条件的に制約を認める人まで無数の思想的内実があるわけだが、そうした思想を持つ人々にとっては多くの国家・地域は制約だらけにみえるだろう。
自分たちの思想を社会に反映させるためには、民主主義の場合にはリバタリアン的思想を持つ候補者に票を投じたり、自分自身が立候補して国の方針を地道に変えていかなければいけないわけだが、それは当然ながらなかなかに大変な道のりである。だが、国のような大きな単位でなくとも、小さな町レベルであれば数百、数千人のリバタリアンが移住してくれば、リバタリアンらの意見を押し通すこともできるだろう。
本書『リバタリアンが社会実験してみた町の話』は、まさにそれをやってみた人たちと町についての話である。舞台はニューハンプシャー州のグラフトンという町で、熊などの野生動物が多く、もともと1000人程度の人口しかない片田舎だ。ニューハンプシャーはもともと自由な気質で知られている州のひとつだが、中でもグラフトンはその傾向が強い土地である。2004年、リバタリアンたちはこのグラフトンに集団移住を呼びかける”フリータウン・プロジェクト”を立ち上げることになる。
と、そんな感じで町の歴史とリバタリアンたちによる社会実験の顛末が語られていくのだが、読んでみれば驚くことに、本書の大半はリバタリアンの社会実験がどうこうよりも熊の話で占められている。入植がはじまった1700年代から熊が多く、熊との戦いはこの地域の宿命といえる。だが、リバタリアンらが集まって”自由”の気風が強化された結果熊に餌をやり続ける人間も許され、州も「熊は基本人を襲わない」として熊の存在を許容し、動物愛護の観点からもその数を減らしたがらず──とそれぞれの思惑が連続し、時折駆除こそなされるもののその数はどんどんと増えていく。
そうして、すっかりグラフトンとその周辺は実質的に熊の楽園と化し、住民は日夜熊が自分たちの生活圏を脅かす恐怖と共に暮らすはめになってしまったのである。本書が描き出していくのはそうした熊と共存していく町になったグラフトンの有り様であり、原題は『A LIBERTARIAN WALKS INTO A BEAR』となっている。
リバタリアンの話をメインに期待して読み始めたのに実際は熊の話ばかりなので期待外れなのだが(邦題にも熊入れてくれ)、一方で町の成立、発展過程。熊に関連した話もちゃんとおもしろく、結果的には満足度の高い作品に仕上がっている。
どのように人々は集まってきたのか?
最初にグラフトンにやってきたのは4人の夢想家である。歴史に残る社会実験の多くは、砂漠や島などの無人地帯に人を集めようとして失敗しているが(インフラ構築に莫大な金がかかるため)、この4人は現存する町の力とインフラを利用することにした。
4人は場所の選定にあたって、”自由な生か、もしくは死”をモットーにするニューハンプシャー州に移住することをまず決定し、その後20の町を検討したのちに、グラフトンへと辿り着いた。商業施設は何もなく、辺鄙な町で、コミュニティらしいコミュニティもない。そしてここの住民は、官僚政治に非協力的で、税金などに反対の立場をとっていた。リバタリアンにぴったりで、土地も広いので移住もできそうだ。
そうして4人は土地を買い、身近な仲間を説得し、掲示板でリバタリアンの移住者仲間を募り始めた。一部の人間に許可をとっていたとはいえ、ほとんどのグラフトン市民にとって寝耳に水の話で、彼らは自分たちに自由を押し付けようとしているなどと猛烈に怒ったが、移住を止められるわけではない。それに、大多数の人間はこの件について無関心をつらぬいていた。結果的に何人のリバタリアンが移住したのか? 国勢調査によれば、町の人口は2000年から10年のあいだに200人以上増えたという。
自由な町にヤバいやつらが集まってくる。
200人以上増えたとはいっても、そのすべてがリバタリアンとは限らない。たとえば、リバタリアンではなく自給自足し、銃などで武装し自分の身を守ることができる状態を目指す、サバイバリストと呼ばれる人たちが、「自由」を目指してフリータウン・プロジェクトに相乗りしてきたのである。『だがフリータウン信者は、少なくとも一つ、重大な計算違いをしていた。グラフトンを究極のフリータウンと呼ぶことで引き寄せられるのは、リバタリアンだけだと思いこんでいたのである。』
フランツは当然ながらグラフトンを選んだ。フリータウン・プロジェクトが発表された場所、いつでも警官が一人か二人しかいない場所。
「あれこれうるさく言ってくる人間はいない。ここはやりたいことができる場所だ。なりたいものになれる場所。何も心配しなくていい」
「自由な町を作ろうと呼びかけたら自由を目的にヤバいヤツらが集まってきた」みたいなひどい状況で思わずここを読んだ時は笑ってしまったが、自由を志す以上、これも当然の結果といえるだろう。
リバタリアンらは町を良い方向に変えたのか?
さて、それはそれとして100人ぐらいはいたであろうフリータウン信者らは町をどう変えたのか? 彼らは町の倹約指向の人々と同盟を組んで、電気代を節約するため街灯を消し、道路の資材や設備を節約するため道を分断した。クリスマスなどの記念日の虚飾を廃し、町計画委員会の2000ドルの予算を50ドルまで減らした。当然だが、グラフトンの公共サービスは穴だらけになり、社会には停滞感が広まっていく。
リバタリアンがサービスの削減を進めるにつれて、その穴から現れたのは個々人が責任を持つ理想的な文化ではなく、種々雑多な森のにわか作りのキャンプであり、一部の人々は下水の漏れなど不衛生な生活状況について苦情を申し立てはじめた。
すべての財政は削減され、警察の数は減り、12年もののパトカーもしょっちゅう修理に出され年間を通じて稼働不可能な日が多くあった──など、ここには住みたくないな……という町へと変質していく。とはいえ税は低いんでしょう? と思うかもしれないが、その税も低いわけではなくて……と、実際にリバタリアンらがこれ以外にどのように町を変えていったのかは、肝の部分なので読んで確かめてもらいたい。
おわりに
熊の話をほとんどしていないが、こうした話の合間合間に住民がいかに熊の被害を受けているのか、そしてなぜそこまで熊の数が増えているのかという歴史的過程。一日にバケツ二つ分の餌を熊に与え続け、熊を餌付けすることに喜びを感じているドーナツ・レディについての物語、集結したサバイバリストたちが町でどのように過ごしているのかなど、この町で起こっていく世にも不思議な物語の数々が語られていく。
リバタリアンらの社会実験の話だけが読みたい人にはお勧めしづらいが(移住者は少なく、その進め方はお粗末なもので、失敗して当たり前で生まれる知見もあまりない)、自由の旗印のもとに集まってきた奇妙な人々と熊の話を読みたい人にとっては大変に楽しめる一冊といえる。