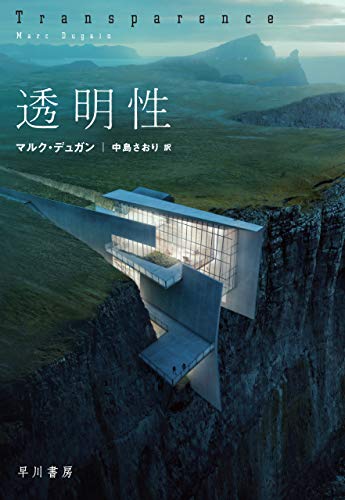で、音源サンプルもいただいて(とてもよかったです。ありがとうございます)発売日も9月15日に決まったので、宣伝ついでにオーディオブックの良さについて紹介しておきたい。僕も2年ぐらい前から熱心にオーディオブックを使うようになり、これって意外と便利だな、と思う局面が多かったからだ。『SF超入門』を買ってもらうかはともかく、オーディオブック自体は使い方次第でとても便利なのでおすすめしたい。
オーディオブックをどこで買うか?
ちなみにオーディオブックを聞ける・購入できるサービスは多々あるが、現状最大手はアマゾンだろう。オーディオブックをアマゾンで買おうとすると3500円ぐらいと(普通の本と比べると)高額になってしまうが、サブスクで読み放題のオーディブルがあって、それだと定額でたくさんの作品を聴くことができる。おそらく、アマゾンでオーディオブックを楽しんでいる人の大多数はこのオーディブルユーザーだろう。
月額が1500円程度なので、もしあなたの読みたい本がオーディブルの読み放題対象に入っているのなら、一冊で買うより確実にオーディブルで聴いた方が安い。そのうえアマゾンは数年前からやたらとオーディブルを普及させようとしており(実際売上が伸びていることもあって、オーディオブックになる本も増えている)、頻繁に割引メールを送ってくるので、タイミングを見ても入っていいかもしれない。
その性質上オーディオブックは本が書籍で刊行されてから数ヶ月経ってから出るのがデフォルトなので、新刊書籍を真っ先に楽しむ用途には向いていないが、刊行から半年程度経つとオーディオブックが出て、オーディブル対象になっているケースが多い。たとえば中国のSF作家劉慈欣の『三体』シリーズは全部聴き放題に入っているし、今年出たばかりの劉慈欣の第一長篇『超新星紀元』も聴き放題対象だ(ただオーディオブック自体の配信日が今年の11月10日からなのでそこからのスタートになるが)。
僕がSF小説の紹介記事を書くと「まだ『三体』も読み終わってないから読めない……」とコメントがつくが、「読め」ないなら「聴く」のも良いだろう。
www.amazon.co.jp
オーディオブックの何が良いか──集中力の問題
オーディオブックの良い点は個人的には大きく二つある。集中力が(目で読むのと比べて)かからないのと、時間の問題だ。前者はいうまでもないと思うが、オーディオブックなら聴いている時目をつぶっていても良いのと、目で文章を追う必要がないので、単純に労力がかからない。電車の移動中は本を読むのに最適な瞬間だが、いちいちカバンから本を出したりしまったりするのが手間(乗り換えがあるとなおさら)だが、オーディオブックなら目をつぶっていても何も問題ないのでとても楽だ。
とはいえ、僕は終日リモートワークで一ヶ月に電車に乗るのは一、二回という生活なので、あまり移動中にオーディオブックを聴くことは少ない。一番多いのは家で寝っ転がっている時だ。僕も若い頃は何時間でも集中して本が読めたものだが、最近は目も悪くなったし、SNSの問題など様々なものがあるせいで気が散って長時間は集中できない。一方でオーディオブックなら目を休めながらも読むことができる。目をつむっているとそのまま寝てしまうこともあるが、それもまた心地よしというものだ。
オーディオブックといえば移動が多い人のためのもの、というイメージが僕にはあったが、家からほとんど出ない人にとってもよい局面は多い。
オーディオブックの何が良いか──時間の問題
オーディオブックのもう一つの利点は「読了までの時間が測りやすい」点にあると思う。特に僕なんかは書評を仕事で書く関係上あー何日締切の原稿を書くために、あれとあれを最低限読んでおかないとーと「読了」の期限が決まっていることが多い。
もちろん期限に間に合うようにがんばって読むわけだが、目で能動的に追っていく読書の場合、はたしていつ読み終わるのか自分でも読めない時が多い。難しい本なら時間がかかるし、簡単な本ならあっという間で、ブレが大きい。それとは別に、さっきの集中力持続問題もあって読了時間の目安が立てづらい。その点オーディオブックなら目で読むのと比べて時間はかかることが多いが、読了までの時間は正確に把握することができる。『超新星紀元』なら、再左営時間は13時間36分なので2倍で聴けば7時間かからずに読み終わるな〜と予測が立つだろう。
オーディオブックの利点はきちんとした俳優や声優の方が読み上げてくれているので、倍速でも聞き取りやすい点にもある。僕はオーディオブックを使うようになる前からスマホの画面認識&読み上げ機能を使って、オーディオブックじゃない作品もKindleの電子書籍で買って音声で聴いていたんだけど(さらにそれをレコーダーに録音してMP3化して、水中イヤホンに入れてプールで泳いだり、アクロバティックなこともしていた)、どうしても機械なので、漢字の正確な読み上げも聞き取りも難しい。オーディオブックをたくさん聴いていると、プロって凄いな、と実感させられる。
note.com
具体的に何を読んでいるのか
みな自分の好きなものを読めばいいわけだが、僕の場合は原稿を書くための資料になりそうな本であったり、少し前で賞をとった作品や話題になった作品をキャッチアップするために使っていることが多い。たとえば少し前は米澤穂信の読んでいなかった作品(『黒牢城』とか)を順々に聴いたし、呉勝浩の『爆弾』も聴いた。
僕の利用例でいうと書評家としての専門といえるSFやノンフィクションは新刊で出た直後に読みたいので紙の本やKindleで読み、ミステリーやビジネス系など専門から少しズレるが話題作をオーディブルでおさえておく、という使い方をしている。なんでもそうだが適材適所なので、ケースに沿った使い方をするのがいいだろう。
一例でいうと、僕の友人は毎朝スーパーに出社して品出しなどの仕事をこなしているのだが、その時いつもオーディブルでなろう系の小説を適当に聴き続けたという。そして、いつのまにかなろう小説博士みたいになっていた。いろんな使い方がある。
おわりに
僕は家の中にずっといるからあれだが、移動が多い人はより助かるだろう。また、オーディオブックになってなかったりオーディブルに入っていない作品はKindle読み上げで聴いているが、こちらについては以前記事も書いているので割愛。
huyukiitoichi.hatenadiary.jp
ここまで書いて気づいてしまったが、『SF超入門』はオーディオブックにはなるが聴き放題の対象には入っていなかった笑 どうにかならないか裏できいておきます。








![家電批評 2021年 11月号 [雑誌] 家電批評 2021年 11月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61zB4IhjgOL._SL500_.jpg)










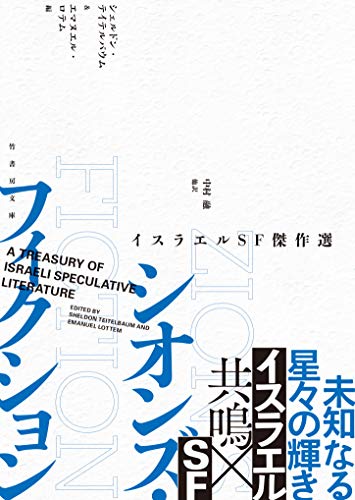
![日本SFの臨界点[恋愛篇] 死んだ恋人からの手紙 (ハヤカワ文庫JA) 日本SFの臨界点[恋愛篇] 死んだ恋人からの手紙 (ハヤカワ文庫JA)](https://m.media-amazon.com/images/I/41rdwbaB2UL.jpg)